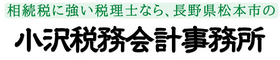相続における公平を保つための特殊な権利 ~代襲相続と遺留分~
相続は、遺言や生前贈与など被相続人の裁量により親族に財産を分け与えたいという考えがあることがおそらく一般的でしょう。
一方で、亡くなった被相続人の財産をできるだけ適切に分け合いたい、または、多く取得したいというような相続人の考えもあります。
このような被相続人、相続人同士の考え方の違いなどにより「円満相続」とはいかないケースも多くあります。
民法では、相続の公平を保つための権利が定められており、税法では、その税金の公平性を確保するための規定があります。
当記事では、相続が発生した時点で本来相続人となるはずであった子や兄弟が先に亡くなっていた場合の権利である代襲相続と、相続人が相続できる財産の割合が少ない場合などに財産取得の一定額が保障される権利である遺留分を取り上げます。

【代襲相続】
・代襲相続とは
代襲相続とならない通常の相続における相続人の範囲や法定相続分については、
【相続の方法】・法定相続人と法定相続分
をご覧ください。
代襲相続とは、相続が発生した時点で本来相続人となるはずであった子や兄弟が先に亡くなっていたとき、先に亡くなっていた子や兄弟に代わり、その子(被相続人の孫、甥姪)に相続権を引き継ぐことができる制度です。
例として、被相続人Aが亡くなった際にAの子であるBが既に亡くなっていた場合、Bの子であるX(被相続人Aの孫)にBが生存していた場合と同等のAの財産を相続する権利があるということになります。
代襲相続において、先に亡くなっていた本来の相続人であるBを被代襲者、新たに相続人となるXを代襲相続人と呼びます。
代襲相続という制度がある理由として、本来引き継ぐことができる財産が亡くなった時系列の前後で変化しないよう公平を保つためということが挙げられます。
被相続人が亡くなった際に被代襲者が存生だった場合は、通常の相続と同様に被代襲者が相続人となり、その被代襲者(相続人)が亡くなった際は、その子である代襲相続人が被代襲者の財産を相続します。
つまり、被相続人より先に亡くなったことでその孫や甥姪が本来引き継ぐことができる財産が受け取れないことを防ぐ、相続順位の補完的な制度となります。
・代襲相続の要件
代襲相続を開始するためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。(一部省略)
① 予定相続人が死亡している
被相続人より先に予定相続人が亡くなるなどにより相続権を失っている必要があります。
死亡以外には、欠格・排除による相続権の剥奪があります。
相続放棄は当てはまりませんので注意してください。
② 代襲相続人が直系卑属又は甥姪であること
直系卑属とは、子・孫・曾孫のような父祖から子孫へ垂直につながる血族を直系血族で下の世代を指します。
被相続人から見ると孫・曾孫にあたり、被代襲者から見ると子・孫にあたります。
養子がいる場合、養子縁組後に生まれた子については代襲相続人になることができますが、養子縁組前の子(連れ子)については代襲相続人になることができません。
直系卑属に関しては、どの世代までいっても相続権があります。
例外として、兄弟の子である甥姪が認められています。
ただし、直系卑属ではないため兄弟の子である甥姪の世代までしか相続権がありません。
・法定相続について
代襲相続が開始した場合、代襲相続人を法定相続人とします。
被代襲者は、相続権がありませんので法定相続人から外れます。
法定相続人が変更した際には、主に相続税の基礎控除や法定相続分が変わります。
ケース①(通常の相続)
被相続人A、配偶者B
子C、子D、子E
Cの子(Aの孫)にあたる孫CX、孫CY、孫CZ
法定相続人は、常に相続人となる配偶者B、第一順位の子C・D・Eの合計4人となります。
孫は、相続人の範囲に含まれないため、法定相続人にはなりません。
相続税の基礎控除は、(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で算出されるため、法定相続人4人=5400万円となります。
法定相続分は、配偶者が1/2、子が合計1/2(子Cが1/6、子Dが1/6、子Eが1/6)となります。
ケース②(代襲相続)
被相続人A、配偶者B
子C、子D、子E(子Cは死亡している)
Cの子(Aの孫)にあたる孫CX、孫CY、孫CZ
法定相続人には、まず、常に相続人となる配偶者B、第一順位の子D・Eが当てはまります。
しかし、第一順位の子Cが死亡しており、代襲相続の要件を満たす孫CX、孫CY、孫CZが新たに相続人となるため、法定相続人は合計6人となります。
相続税の基礎控除は、(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で算出されるため、法定相続人6人=6600万円となります。
このように、代襲相続のほうが基礎控除が大きくなるケースもありますので留意してください。
法定相続分について、子Cが存生していた場合では、配偶者が1/2、子が合計1/2(子Cが1/6、子Dが1/6、子Eが1/6)となります。
被代襲者である子Cが受け取るはずであった財産は1/6であるため、代襲相続人である孫CX、孫CY、孫CZがその割合と同等の権利を引き継ぎます。
つまり、ケース②の法定相続分は、配偶者が1/2、子Dが1/6、子Eが1/6、子Cの子が合計1/6(孫CXが1/18、孫CYが1/18、孫CZが1/18)となります。
また、孫への相続というと、一親等の血族及び配偶者以外にあたるため相続税額の2割加算が考えられますが、代襲相続の場合は孫自身が法定相続人となるため2割加算の要件には当てはまりません。

【遺留分】
・遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人の相続財産の取得を保障する制度です。
予定被相続人は、自分が形成した自分の財産を生前贈与や遺言などにより自分の裁量で処分する自由が認められています。
一方で、予定相続人は、被相続人の財産形成に貢献した部分を引き継ぐ権利があるとされています。
そのような被相続人の財産処分の自由と相続人の権利との調和を取るために遺留分制度があります。
一例として、
・配偶者に全財産を生前贈与したことにより、子供兄弟の相続できる財産がない
・遺言により配偶者に全財産を相続させる旨があり、子供兄弟の相続できる財産がない
というとき、子供兄弟は、配偶者に対して遺留分を請求することができます。
その他にも、被相続人が孫や愛人などの法定相続人以外の第三者に多くの財産を譲ってしまうことや前妻の子への財産分与をしなかったために遺留分を請求されるケースなどもあるそうです。
相続財産の遺留分については、その保障分は、贈与契約や遺言などの財産処分の自由よりも優先されます。
注意しなければならないことは、相続財産の遺留分は自然に相続されるものではないということです。
生前又は相続開始による財産分与の結果、遺留分という相続人の保証分が侵害されていることを主張・請求(減殺請求)する必要があります。
・遺留分請求の要件
遺留分が認められるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。(一部省略)
① 遺留分請求対象者である相続人(本人)が直系親族であること
配偶者、親や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属が当てはまります。
第三順位である兄弟姉妹は、被相続人の生活や財産形成などの関係性の低さから除外されますので注意してください。
② 相続放棄、遺留分放棄、相続権の欠格・排除がされていないこと
主に、相続放棄した人は除外されます。
③ 減殺請求者(本人)の遺留分が侵害されていること
実際の相続財産が遺留分に満たない場合、減産請求ができます。
減殺請求をする人は、遺留分が侵害されていると主張する本人である必要があります。
なお時効は、減殺事実を知った日から1年又は相続開始から10年です。
・遺留分の算定と財産の範囲
遺留分の金額を算定するにあたって、遺留分の割合が定められています。
通常は、被相続人の財産の1/2とされており、例外として直系尊属である親のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3となっています。
この割合は、被相続人の財産に対する遺留分の割合であるため、言い換えると、
相続人の法定相続分の1/2、被相続人の親のみが相続人の場合のみ法定相続分の1/3
ということになります。
代襲相続の場合も、同等の割合で遺留分を算定することになりますが、被代襲者が子で代襲相続人が孫の場合には孫に遺留分が認められますが、被代襲者が兄弟で代襲相続人が甥姪の場合には上記要件①の直系親族に該当しないため遺留分が認められません。
また、遺留分の話し合いがまとまらず減殺請求をしたり、減殺請求調停まで行ってしまうような場合では相続税の申告期限を超えてしまうこともあります。
申告期限を超えてしまうと延滞税を課せられたり決定処分が行われることがあるため、実務上、現在の相続状況で申告をすることで回避することが多いと思われます。
その後、相続税申告後に遺留分の話し合いや減殺請求の結果、相続財産が増減した場合は、相続税の修正申告又は減額更正などが必要となりますので注意してください。
遺留分の減殺請求により取得できるであろう個々の金額は、
財産金額 × 個々の遺留分割合 - (相続財産+特別受益等)
となります。
なお、財産金額は、被相続人が亡くなった際に所有していた実際の財産金額ではなく、民法上の財産金額となります。詳しくは、後述します。
遺留分の算定についていくつか例を紹介します。
便宜上、財産はすべて現金とします。
ケース①
総財産 12000万円
被相続人A、配偶者B
子C、子D、子E
遺言により子Cが総財産を取得(3年以内の贈与により取得したケースも同様)
子Cが遺言どおり総財産を取得し(贈与を受け)、財産を独占するなどの場合は、
相続人かつ直系親族である配偶者B、子D、子Eは、多額の特別受益などがある場合を除いて子Cへ個々の遺留分を主張・請求することができます。
法定相続分は、配偶者Bが1/2、子C・子D・子Eがそれぞれ1/6ずつであるため、遺留分は、配偶者Bが1/4、子D・子Eが1/12ずつとなります。
子Cが総財産を取得した場合
配偶者B 0万円
子C 12000万円
子D 0万円
子E 0万円
子Cが総財産を取得し、配偶者B、子D、子Eが遺留分を主張・請求した場合
配偶者B 3000万円(遺留分1/4)
子C 7000万円
子D 1000万円(遺留分1/12)
子E 1000万円(遺留分1/12)
ケース②-⑴
総財産 12000万円
被相続人A、配偶者B
被相続人の母AX
遺言により配偶者Bが総財産を取得(3年以内の贈与により取得したケースも同様)
配偶者Bが遺言どおり総財産を取得し(贈与を受け)、財産を独占するなどの場合は、
相続人かつ直系親族である被相続人の母AXは、多額の特別受益などがある場合を除いて配偶者Bへ遺留分を主張・請求することができます。
法定相続分は、配偶者Bが2/3、被相続人の母AXが1/3であるため、遺留分は、被相続人の母AXが1/6となります。
配偶者Bが総財産を取得した場合
配偶者B 12000万円
母AX 0万円
配偶者Bが総財産を取得し、母AXが遺留分を主張・請求した場合
配偶者B 10000万円
母AX 2000万円(遺留分1/6)
ケース②-⑵
総財産 9000万円
被相続人A、配偶者B(配偶者Bは離婚又は相続発生前に死別)
被相続人の母AX
遺言により甲法人が6000万円、甲法人の代表乙(血縁関係なし)が3000万円の財産を取得
甲法人及び代表乙が遺言どおり総財産を取得し、財産を独占するなどの場合は、
相続人かつ直系親族である被相続人の母AXは、多額の特別受益などがある場合を除いて甲法人及び代表乙へ遺留分を主張・請求することができます。
なお、配偶者Bは離婚(死別)しているため、相続権はありません。
法定相続分は、被相続人の母AXしか法定相続人がいないため100%ではありますが、遺留分については、例外の直系尊属である親のみが相続人である場合にあたるため、被相続人の母AXが1/3となります。
遺留分を侵害する財産受取人及び財産種類(当ケースは現金のみ)が複数の場合は、その割合に応じて決定されます。
甲法人及び代表乙が財産を取得した場合
母AX 0万円
甲法人 6000万円
代表乙 3000万円
甲法人及び代表乙が財産を取得し、母AXが遺留分を主張・請求した場合
母AX 3000万円(遺留分1/3)
甲法人 4000万円(6000万円-9000万円×1/3×6000万円/9000万円)
代表乙 2000万円(3000万円-9000万円×1/3×3000万円/9000万円)
ケース③
総財産 12000万円
被相続人A、配偶者B
被相続人Aの兄弟C、兄弟D(相続発生前に兄弟Dは死亡)
兄弟Dの子DX(甥DX)
遺言により甲法人が総財産を取得
まず、法定相続人で遺産分割を行う場合、配偶者と兄弟姉妹の相続にあたるため、本来の法定相続人は、配偶者B、兄弟C、兄弟Dとなりますが、兄弟Dは相続発生前に死亡していますので、兄弟Dを被代襲者、甥DXを代襲相続人とした代襲相続が起こります。
これにより法定相続分は、配偶者Bが3/4、兄弟C・甥DXがそれぞれ1/8ずつとなります。
しかし、第三者である甲法人へ遺言により総財産を相続させる旨があるため、遺言通りに遺産分割を行うと親族へ財産は渡りませんが、相続人かつ直系親族である配偶者Bは、多額の特別受益などがある場合を除いて甲法人へ遺留分を主張・請求することができます。
ただし、甲法人が遺言どおり総財産を取得し、財産を独占するなどの場合は、直系親族ではない兄弟Cは、遺留分を主張・請求することができません。
同様に甥DXも兄弟Dの相続権と同等の権利を引き継いでいるため、直系親族ではないことを理由に遺留分を主張・請求することができません。
遺留分は、配偶者Bが1/2となります。
仮に遺言がなく、法定相続分で遺産分割を行った場合
配偶者B 9000万円
兄弟C 1500万円
甥DX 1500万円
甲法人 0万円
甲法人が総財産を取得し、配偶者Bが遺留分を主張・請求した場合
配偶者B 6000万円(遺留分1/2)
兄弟C 0万円(遺留分なし)
甥DX 0万円(遺留分なし)
甲法人 6000万円
遺留分を算定する際の財産基準は、遺産分割時と同様に税法上の相続財産ではなく民法上の相続財産をいいます。
詳しくは、 相続における民法と税法の違い をご覧ください。
簡潔にまとめると、遺留分における相続財産は時価であり、特別受益などを考慮したものを被相続人の総財産とし、同様に、相続人の遺産分割による財産の法定相続分や遺留分の算定の際も個別に加減する必要がありますので注意してください。
【まとめ】
相続においての相続人の権利の公平を保ち、保護する観点より様々な規定があります。
代襲相続について知識がない場合、自分の配偶者や子がいることにより、子(孫の親)と死別し残された孫へ財産が渡らない心配から焦って贈与をしてしまい、より高額な税金がかかってしまう、ということも考えられます。
被相続人が法定相続人の遺留分を考慮せず、遺言を作成したことによって遺族がトラブルになるケースも多くあります。
また、生前贈与した結婚資金・住宅資金・特別受益などを考慮しないために、遺産分割がうまくいかなかったり遺留分を侵害するケースも多くあります。
遺留分を侵害した遺産分割の場合、話し合いによる再分割が上手くいかなければ遺留分減殺請求を行うことになりますし、減殺請求がうまくいかなければ調停・裁判まで行うことになります。
税金面でもより高額になってしまったり手続きが増えてしまうこともあるため、予定被相続人が生前のうちに自分の財産をある程度正確に把握し、それに応じた生前贈与や遺言を作成することが重要だと考えます。
〈こちらの記事は、2018/8/23更新記事を参考に作成しています。〉